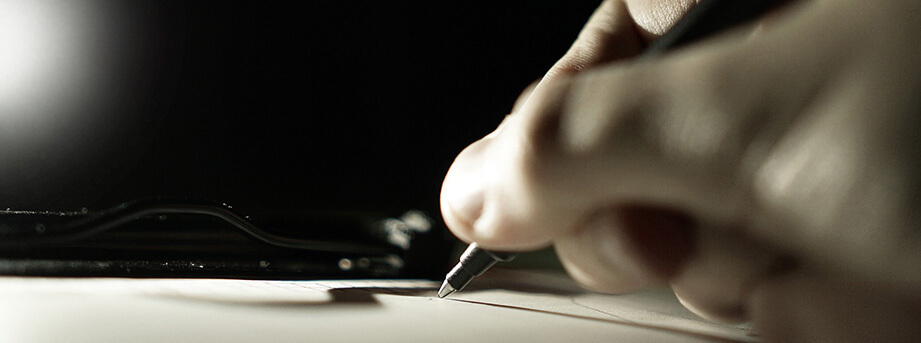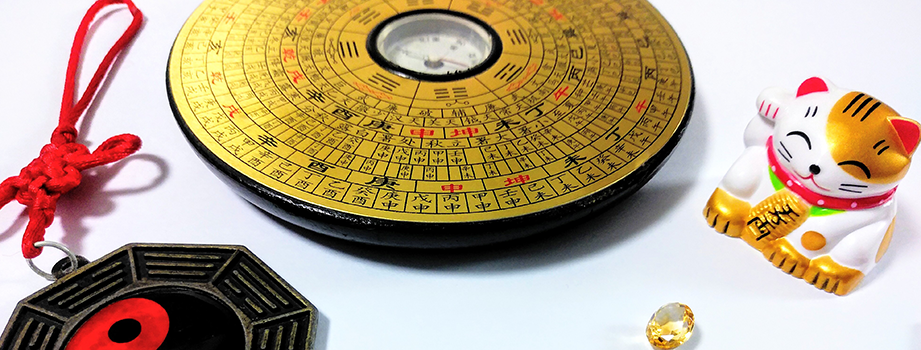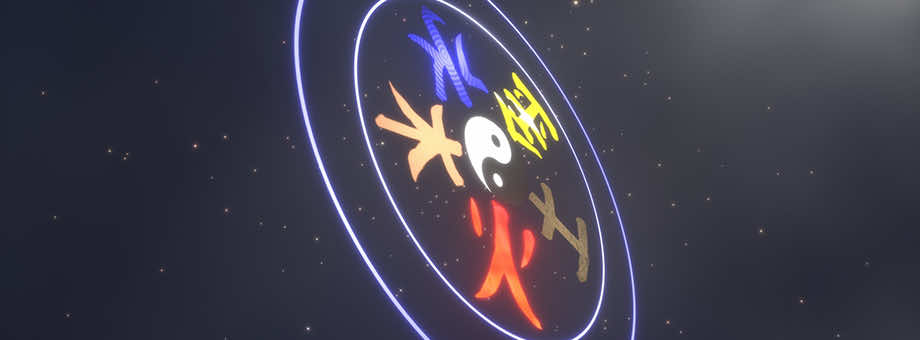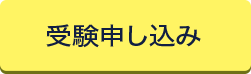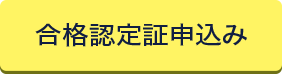宿曜占星術アドバイザー資格認定試験

宿曜占星術アドバイザー資格
当協会指定の認定講座
宿曜占星術アドバイザー資格試験概要
宿曜占星術アドバイザーとして、宿曜占星術の基礎、宿曜の分類、開運法、二十七宿、二十七宿の吉凶、九曜星について、九曜がもたらす運勢、三・九の秘宝による人間関係や日の吉凶、十二宮についてなど、宿曜占星術に関する幅広い知識を有していることが証明されます。資格取得後は、宿曜占星術アドバイザーとして活躍でき、自宅やカルチャースクールなどで講師活動ができます。
| 受験資格 | 特になし |
|---|---|
| 受験料 | 10,000円(消費税込み) |
| 受験申請 | インターネットからの申込み |
| 受験方法 | 在宅受験 |
| 合格基準 | 70%以上の評価 |
| 資格試験内容 | 宿曜占星術/ 宿曜占星術とは/ 宿星の分類/ 宿曜における開運法/宿の素質/ 角宿・亢宿/ 房宿/ 心宿・尾宿/ 箕宿・斗宿/ 女宿・虚宿/ 危宿・室宿/ 壁宿・奎宿/ 婁宿・胃宿/ 昴宿・畢宿/ 觜宿・参宿/ 井宿・鬼宿/ 柳宿・星宿/ 張宿・翼宿/軫宿/白日と黒日/二十七宿の吉凶/十二宮についてなどの知識が問われます。 |
| 試験日程 | 以下参照 |
宿曜占星術とは
インド占星術をベースにした日本の占星術で、月の周期(白道)を27の宿と宿道十二宮に分け、月の状態によって人の性質や吉凶、また、吉凶となる日を占う方法を用いた占星術です。暦は旧暦を扱い、智慧の菩薩である、文殊菩薩が28の宿をつくり、暦を完成させたという伝承を元にしています。中国,唐代のインドの二十八宿七曜などを述べた選訳書『宿曜経』、正式名『文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善悪宿曜経』を弘法大師の空海が翻訳して、密教徒などが研究した占星術であるのが起源と伝えられています。占星術を宿曜道、占星術を行う者を宿曜師と呼び、陰陽道の陰陽師と勢力を二分した占星術です。戦国時代に用いられ、江戸幕府はこの占星術を禁止したと言われています。密教の僧によって門外不出の占術として受け継がれてきた占いで、性格や能力を占う事が出来ます。自分と相手の「宿」の位置関係を調べることによって導き出される相性診断としても用いられることが多いです。
宿曜占星術について
平安時代には、陰陽師たちも密かに使っていたとも伝えられる 宿曜占星術は、生まれ日の「宿」をまず調べ、宿から性格など個人のことが占えます。相性を占うときは、自分の宿が頂点に来ている27種の宿が星座のように書き込まれた『宿曜盤』を用いて、相性や過去現在未来を読みとる要素を読み解き、それぞれ相手や未来の日の宿を探して自分との関係を占っていきます。 使用する道具は生年月日を宿に換算する表で、西洋占星術が太陽の通り道、黄道を中心とした占いであるのに対し、宿曜占星術は月の通り道、白道を中心として、月の運行を宿曜12宮を配するのが特徴となっています。月の周期を27の宿と宿道12宮に分け、月の状態によって人の性質や吉凶、また、吉凶となる日を占うことが基本です。宿曜12宮については、一週間の曜日の語源ともなっています。自分の宿と相手の宿から、相性を占うこともできるので、命・業胎・栄親・危成・安壊・友衰の関係で占いを表すことが出来ます。
試験実施日程
-
2025年8月実施
資格検定試験期間 2025年8月20日〜25日 受験申込期間 2025年7月1日〜31日 受験票
試験問題
解答用紙発送日随時 答案提出期限 2025年8月30日 合否発表日 2025年9月20日
資格取得で目指せる職業
宿曜占星術アドバイザー
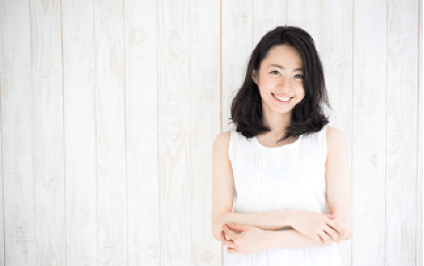 起源は、弘法大師の空海が原典を翻訳し、広めていた宿曜経を密教徒たちが研究したことから日本独自の占い方法が宿曜占星術です。研究がすすむにつれ道教の概念も取り入れられ、現代でもこの占星術を生業とする宿曜師は日本国内に存在しています。戦国時代から政治に影響を与え、貴族政治から武家政治に移行した時代には、占星術も武家に流れ、特に軍略に用いられるようになった占星術です。中国の三国時代には諸葛孔明が軍略に占星術を用いただけでなく、織田信長や武田信玄も戦の際には未来を占っていたなど、宿曜占星術アドバイザーはこういった宿曜占星術の歴史と、具体的な占い方法を習得した、他人に宿曜占星術を教えたり、あるいは宿曜占星術の占い方をアドバイスする立場として活躍出来る民間資格です。より本格的な宿曜師として独立を考える際にも、この資格を通じて習得した事を更に発展して経験を積めば、宿曜占星術アドバイザーは有利となる資格でしょう。
起源は、弘法大師の空海が原典を翻訳し、広めていた宿曜経を密教徒たちが研究したことから日本独自の占い方法が宿曜占星術です。研究がすすむにつれ道教の概念も取り入れられ、現代でもこの占星術を生業とする宿曜師は日本国内に存在しています。戦国時代から政治に影響を与え、貴族政治から武家政治に移行した時代には、占星術も武家に流れ、特に軍略に用いられるようになった占星術です。中国の三国時代には諸葛孔明が軍略に占星術を用いただけでなく、織田信長や武田信玄も戦の際には未来を占っていたなど、宿曜占星術アドバイザーはこういった宿曜占星術の歴史と、具体的な占い方法を習得した、他人に宿曜占星術を教えたり、あるいは宿曜占星術の占い方をアドバイスする立場として活躍出来る民間資格です。より本格的な宿曜師として独立を考える際にも、この資格を通じて習得した事を更に発展して経験を積めば、宿曜占星術アドバイザーは有利となる資格でしょう。
- 宿曜占星術アドバイザー資格取得
宿曜占星術アドバイザーの仕事内容
(占い1回5,000円前後)
宿曜占星術の「三九の秘法」は相性を見るの効力を発揮すると言われ、「三九の秘法」とは自分の本宿星を「命」として逆時計回りの9番目を「業」、18番目を「胎」として人間関係における相性を見ます。また命から業までが「一・九の法」といい、業から胎までが「二・九の法」、胎から命までが「三・九の法」といい、この三つを合わせ「三・九の秘宝」と呼びます。その中で人間関係性の相性別に分け、それが命・業胎・栄親・危成・安壊・友衰の6つ関係で表せることが出来るとしています。自分と同じ宿星である命宿のグループと同じグループの胎業、互いに栄えることができる栄親、似た者同士の関係の友衰、異質で依存しない関係性の危成、勝てる関係性や負ける関係性の安壊という風にカテゴリにわけることになります。宿曜占星術は、ほぼ相性診断のようなもので、宿曜占星術アドバイザーの仕事はこの占い方法を他人にアドバイスすることになります。習得難易度は比較的高いかもしれません。
二十七宿鑑定インストラクター
 二十八宿の一つ南方朱雀七宿の第4宿である『星宿』の分割法の一つ、月の見かけの通り道である白道を、27の区域に等分割した二十七宿を、人の運勢と照らし合わせて見るのが二十七宿鑑定です。宿曜占星術の基本となるもので、白道とは、天球上における月の見かけの通り道(大円)のことで、旧暦(太陽太陰暦)における月日がわかれば、自動的に二十七宿が決まるようになっています。例えば、直日決定法では中国旧暦11月1日は、「斗」という風になります。宿曜道に於いて、日の吉凶やその日に生まれた人間の運命などを占う際に重要となる概念は『直日 (ちにち)』と言われ、二十七宿鑑定には、この直日決定法を用いることになります。つまり二十七宿鑑定インストラクターとは、この直日決定法を習得して他人に指導出来る知識を持った、資格のインストラクターということになります。宿曜占星術の基本となる概念を学ぶことになるので、宿曜占星術を本格的に始める前に資格を所得した方が良いかもしれません。
二十八宿の一つ南方朱雀七宿の第4宿である『星宿』の分割法の一つ、月の見かけの通り道である白道を、27の区域に等分割した二十七宿を、人の運勢と照らし合わせて見るのが二十七宿鑑定です。宿曜占星術の基本となるもので、白道とは、天球上における月の見かけの通り道(大円)のことで、旧暦(太陽太陰暦)における月日がわかれば、自動的に二十七宿が決まるようになっています。例えば、直日決定法では中国旧暦11月1日は、「斗」という風になります。宿曜道に於いて、日の吉凶やその日に生まれた人間の運命などを占う際に重要となる概念は『直日 (ちにち)』と言われ、二十七宿鑑定には、この直日決定法を用いることになります。つまり二十七宿鑑定インストラクターとは、この直日決定法を習得して他人に指導出来る知識を持った、資格のインストラクターということになります。宿曜占星術の基本となる概念を学ぶことになるので、宿曜占星術を本格的に始める前に資格を所得した方が良いかもしれません。
- 二十七宿鑑定インストラクター資格取得
二十七宿鑑定インストラクターの仕事内容
(鑑定1回3,000円前後)
二十七宿鑑定は主に中国の旧暦を使うこととなるので、多くの二十七宿鑑定で採用されています。宿曜占星術では独自のホロスコープと似たような表が用いられますが、宿曜占星術のホロスコープは三つの円で構成され、外側の円は『十二宮』といい、一年の月の単位を現し、中側の円は、二十七種類の人間のタイプを現し『二十七宿』と言います。二十七宿は、人間の運命を現すことになります。内側の円は、「三・九の秘法」という、対人関係や日々の吉凶を現すというように、ホロスコープは構成されているわけです。月が地球を一周するのに、27日から28日掛かることから一日ごとに星を当てはめ「宿」としたので、『二十七宿』と呼ばれています。西洋占星術は12星座ですが、月の運用を用いている宿曜日占いは27の星を祀る星占いとなるので、二十七宿鑑定インストラクターの仕事は、この占い対象者の星を調べるという鑑定になるわけです。宿曜占星術は占い対象者と関係のある人も占いの対象に出来ますが、二十七宿鑑定の場合は、単に一人の対象者の運勢のみを占うことも出来ます。
占い師
 古代から伝承されて来た占い方法を習得し、占星術、易学、タロットカードなどで決まったルールに基づいて、他人の置かれた宿命や運命、性格や人間関係などを分析し、現状の改善や今後や将来に好転する行動や仕事やプライベートでの人付き合い、自分の考え方を改めたりする、他人にアドバイスを行う相談者が現代の占い師です。ネットや路上で個別に1対1の占いを行ったり、特定の施設で団体やグループに登録して、募集を募って、有料で占いを行って生業とします。結婚や転職、恋愛などの人生の転機における、能動的にはどうしようも出来ない問題について、古代の方法を用いて理解しようとする手段で、昔から若い女性を中心に人気がある職業です。景気に左右されない職種であるのも特徴でしょう。この仕事には年齢制限が無く、経験と習熟度がそのまま占いスキル、占いの信憑性に繋がっているので、一生涯出来る仕事という事も出来ます。占い師の人口は統計が無いので不明ですが、日本全国、副業から本業まで多数の占い師が活躍しているのは間違いありません。
古代から伝承されて来た占い方法を習得し、占星術、易学、タロットカードなどで決まったルールに基づいて、他人の置かれた宿命や運命、性格や人間関係などを分析し、現状の改善や今後や将来に好転する行動や仕事やプライベートでの人付き合い、自分の考え方を改めたりする、他人にアドバイスを行う相談者が現代の占い師です。ネットや路上で個別に1対1の占いを行ったり、特定の施設で団体やグループに登録して、募集を募って、有料で占いを行って生業とします。結婚や転職、恋愛などの人生の転機における、能動的にはどうしようも出来ない問題について、古代の方法を用いて理解しようとする手段で、昔から若い女性を中心に人気がある職業です。景気に左右されない職種であるのも特徴でしょう。この仕事には年齢制限が無く、経験と習熟度がそのまま占いスキル、占いの信憑性に繋がっているので、一生涯出来る仕事という事も出来ます。占い師の人口は統計が無いので不明ですが、日本全国、副業から本業まで多数の占い師が活躍しているのは間違いありません。
- 占い師資格取得
占い師の仕事内容
最近では、知名度のある特定の占い専門サイトに占い師が個別に登録して、サービス利用者が必要な費用を払って、占い師を指名、フリーダイヤルで電話を使っての占いを行うという業態が大変増えています。他には都心部の繁華街などの特定の場所を借り、『占いの館』などに雇用、あるいは派遣され、週末などに占い師が常駐して、占いを有料で受け付ける業態などがあります。易者のように個人事業主の場合は、様々な公共交通機関の側に、移動可能な簡易な椅子とテーブルを設置し、手相や運勢占い、人生相談などを全国を巡りなら、様々な人を占うという巡業のような形態があります。最近では数が減りましたが、『~の母』というのような人気の占い師は、常に行列が出来るほど集客力、収益性が高く、占い師としてだけで生計が成り立っている例がありました。それだけの人気になるためには、特定の場所で長年占いを行ない、的中率やアドバイスのスキルを磨く必要があり、それなりの努力も息の長いものとなります。
カルチャースクール講師
 広義の意味では、各国の言語文化芸術に触れる機会を提供する日本でいう文化センターも含まれ、社会人のための社会教育の機会を提供する民間の教養講座という役割がカルチャースクールです。1980年代以降に一般的な呼称として定着していったことから、日本が戦後からの復興によって生活が豊かになり、それに伴って仕事とは違う教養を身に着けたい要望から普及してきたと言われています。現在では、高齢者向けの大学が行うオープンカレッジも、カルチャースクールのカテゴリに含まれるようになっています。新聞社や放送局などマスメディアが提供する講座が規模が大きく、教室の数も多いのが特徴で、企業が自社製品や自社サービスを宣伝・普及するために、材料、資材を提供して有料で開催する場合も含まれます。主に文化史・文学・歴史などの教養、外国語、書道・手芸・生花・絵画・陶芸などの美術、音楽、ダンスやヨーガなどは一般的で、これに最近では占いや、ワークショップなどもカルチャーセンターやカルチャースクールでは教えられています。そこで働く専任講師がカルチャースクール講師です。
広義の意味では、各国の言語文化芸術に触れる機会を提供する日本でいう文化センターも含まれ、社会人のための社会教育の機会を提供する民間の教養講座という役割がカルチャースクールです。1980年代以降に一般的な呼称として定着していったことから、日本が戦後からの復興によって生活が豊かになり、それに伴って仕事とは違う教養を身に着けたい要望から普及してきたと言われています。現在では、高齢者向けの大学が行うオープンカレッジも、カルチャースクールのカテゴリに含まれるようになっています。新聞社や放送局などマスメディアが提供する講座が規模が大きく、教室の数も多いのが特徴で、企業が自社製品や自社サービスを宣伝・普及するために、材料、資材を提供して有料で開催する場合も含まれます。主に文化史・文学・歴史などの教養、外国語、書道・手芸・生花・絵画・陶芸などの美術、音楽、ダンスやヨーガなどは一般的で、これに最近では占いや、ワークショップなどもカルチャーセンターやカルチャースクールでは教えられています。そこで働く専任講師がカルチャースクール講師です。
- カルチャースクール講師資格取得
カルチャースクール講師の仕事内容
カルチャーセンター、カルチャースクールによって講師料は異なりますが、 一般的には売上の40%が相場となっています。一般的には、講義が終わって期間を終えてから振り込まれる事が多く、ギャランティーという形で報酬を受け取るのが一般的です。「カルチャースクール運営スタッフ」という形でも雇用はあり、単に講師だけではなく、その事業者の運営に従ってカリキュラムを行うようなスタッフが講師を兼任する場合もあります。文化史・文学・歴史などの教養、外国語、書道・手芸・生花・絵画・陶芸などの美術などのカテゴリの場合は、それぞれその道のプロフェッショナルが専任講師として活躍していることが多く、民間資格所有者もこれに含まれます。講習が不定期の場合も多い為、継続的な給与としての報酬はあまり少なく、殆どが一定期間の講習後にギャラが指定口座に振り込まれる形を採用しています。受講者は低学年から幼児、中高年から高齢者まで世代は非常に幅広く、総じて人間関係構築が優秀でコミュニケーション力が高いことが求められます。
受験申し込み
受験を希望される方は以下の申込みページからお申込み下さい。